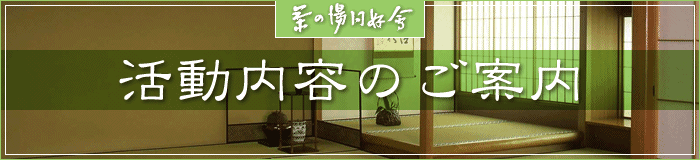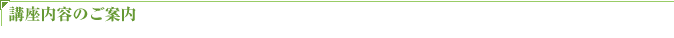 |
|
講座名・講師 |
日 時 |
概 要 |
禅の風
-『無門関』
泉田玉堂先生
|
7月3日(水)
午後1時半~3時
(第2回)
|
隔月第1水曜日(5月は第2水曜日)
於:7階安与ホール
*全5回 会費:15,000円
(令和6年5月~7年3月分)
|
|
-実物で味わう-
茶掛けの消息
増田孝先生
|
7月8日(月)
午前11時~12時半
(第2回)
|
毎月第2月曜日(10月、11月は第3月曜日)
於:7階安与ホール
瑞竜院日秀と思われる仮名消息
いつの宮貞子内親王の仮名消息
*全5回 会費15,000円
(令和6年6月~11月分)
|
|
三千家歴代2熊倉功夫先生
|
7月12日(金)
午後1時半~3時
(第5回)
|
毎月第2金曜日(3月は第5金曜日)
於:7階安与ホール
*全6回 会費:18,000円
(令和6年3月~9月分)
|
|
茶陶が語る
茶の湯の歴史3
赤沼多佳先生
|
7月18日(木)
午前10時半~12時
(第2回)
|
毎月第3木曜日(3月は第2木曜日)
於:7階安与ホール
*全10回 会費:30,000円
(令和6年6月~7年5月分)
|
|
第40回
茶室見学会
田野倉徹也先生
|
7月16日(火)
午前8時15分~16時30分頃
申込受付:キャンセル待ち受付中
|
午前8時15分小田原駅周辺に集合
定員22名
於:箱根美術館、MOA美術館[箱根・熱海]
|
新講座
『山上宗二記』を
精読する
竹内順一先生
|
7月26日(金)
午後1時半~3時
(第1回)
|
毎月第4金曜日(9月、12月、6月は第3金曜日)
於:7階安与ホール
茶の湯の歴史 その1
*全20回
会費:30,000円(令和6年7月~7年6月分/10回)
|
|
| 茶道夏期大学
|
7月28日(日)・29日(月)・30日(火)
午後1時~4時15分
(第52回)
|
於:7階安与ホール
| *会費:会員20,000円
(資料代含む・懇親会費別)
|
|
新講座
名物籠に学び、
籠を編む3
不昧公ゆかりの隅田川菓子器(花入)
池田瓢阿先生
|
9月5日(木)
午後1時半~3時
(第1回)
|
毎月第1木曜日(10月は第5木曜日)
於:7階安与ホール
籠の基本(講座1)
*全4回 会費:20,000円(材料費別途)
(令和6年9月~12月分)
材料費:16,000円(隅田川菓子器/白竹/筒代込み) |
|
「茶書に学ぶ
茶の湯の歴史」
原田茂弘先生
|
9月21日(土)
午後1時半~3時
(第3回)
|
隔月第3土曜日
於:7階安与ホール
③茶会記にみる茶の湯の具体像
*全5回 会費:15,000円
(令和6年4月~7年2月分)
|
|
|
表千家茶事教室 長澤保人先生
|
9月27日(金)
席入:午前11時 (第3回)
|
受付:席入30分前6階にて
於:9階柿傳茶席
|
第20回
茶の湯同好会茶会
潮田洋一郎氏
|
10月18日(金)
|
|
|
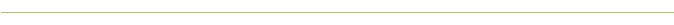 |
-実物で味わう-【茶掛けの消息】 増田孝先生
お席入りし、床の茶掛けを拝見します。そこには茶会のテーマとなる書や絵が飾られています。それは亭主のご馳走のひとつであり、ドラマの始まりなのです。さりげなく味読して茶事が進められるために、くずし字の知識はたいへんに役に立つでしょう。講師とともに現物を見ながら鑑賞のポイントを掴みます。 増田孝 |
| |
| 講座内容 |
令和6年7月8日(月) 瑞竜院日秀と思われる仮名消息
いつの宮貞子内親王の仮名消息
|
| 講 師 |
増田孝氏(愛知東邦大学客員教授) |
| 日 時 |
毎月第2月曜日(10月、11月は第3月曜日) 午前11時~12時半
①令和6年6月10日(月):終了
即位に関する二条為氏の書状、千姫付の女房刑部卿の仮名消息
②7月8日(月)
瑞竜院日秀と思われる仮名消息、いつの宮貞子内親王の仮名消息
③9月9日(月)
一安軒宛の南化玄興書状、近衛前久書状
④10月21(月)
建武三年の起請文、烏丸光広書写の藤原家隆和歌懐紙
⑤11月18日(月)
東本願寺宛の近衛信尋書状、榎十左衛門宛の清巌宗渭書状
|
| 場 所 |
柿傅7階安与ホール |
| 会 費 |
会員:15,000円(全5回分)
*別途毎回、講座の資料代(1回分)100円をいただいております。 |
| 申 込 |
TEL.03-3352-5120 |
|
| |
増田孝氏 略歴
書跡史研究家。博士(文学)。東京教育大学教育学部芸術学科卒業。専攻は日本の書の歴史的研究。現在愛知東邦大学客員教授。
永青文庫評議員。書の鑑定家としてもテレビ東京「開運!なんでも鑑定団」で活躍中。 |
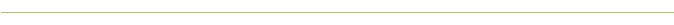 |
【茶書に学ぶ茶の湯の歴史】 原田茂弘先生
茶の湯の歴史をひもとくうえで、茶書は重要な資料です。茶書を読むことにより、茶の湯が直面してきた時代や文化史的な背景を学ぶことができます。また、茶書を著した人の茶の湯へのおもいや理念も知ることができます。今日に伝わるいろいろな茶書を読みながら、茶書とは何かをあらためて考えてみたいと思います。 原田茂弘 |
| |
| 講 師 |
原田茂弘氏(表千家不審菴文庫主席研究員) |
| 日時・内容 |
令和6年4月~7年2月分 隔月第3土曜日
午後1時半~3時
講座内容
①令和6年4月20日(土)茶の湯の聞書と伝書:終了
②6月15日(土)茶会記の成立と変遷:終了
③9月21日(土)茶会記にみる茶の湯の具体像
④11月16日(土)道具帳・蔵帳・名物記の世界
⑤令和7年2月15日(土)茶書にみる茶の湯の理念
※途中回からの受講も可能です。 |
| 開 講 |
令和6年4月20日(土) |
| 場 所 |
安与ホール(安与ビル7階) |
| 会 費 |
1万円5千円(全5回分) |
| 申 込 |
TEL.03-3352-5120 |
|
| |
原田茂弘氏 略歴
昭和38年、広島県生まれ。筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科単位取得退学。研究テーマは日本茶道史。茶の湯文化学会理事。著書に『茶道教養講座16茶書は語る』(淡交社)、主な論文に「千宗旦と三千家の成立」(『講座 日本茶の湯全史』第二巻、思文閣出版)、「千家と江戸の豪商冬木家」(『茶の湯研究 和比』第十一号、不審菴文庫)、「紀州徳川家付家老 水野忠昭と茶の湯」(『茶の湯研究 和比』第十二号)など。 |
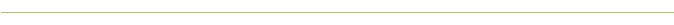 |
【香の文化史】 畑正高先生 終了しました
香は仏教伝来と共にわが国に伝えられました。穏やかな風土に育まれた日本人の繊細な感性は、はるばる南方から届けられる貴重な香料と出会い、おおよそ千四百年に及ぶ歴史を通して、独自の香りの世界を育んできました。
日本の文化史からみて兄弟ともいえる茶の湯と香の関係に注目し、王朝貴族から今日まで受け継がれてきた香文化の楽しさを見つめてみたいと思います。 畑正高 |
| |
| 講座内容 |
令和3年11月11日(木) 芸能と香 |
| 講 師 |
畑正高氏(株式会社松栄堂 代表取締役社長) |
| 日 時 |
毎月第2木曜日(4月は第4木曜日)
午後1時半~3時
①令和2年2月20日(木)「和様開化」:終了
②11月5日(木)「王朝文化と香」:終了
③令和3年4月22日(木)「婆娑羅と香」:終了
④7月8日(木)「茶の湯と香」:終了
⑤10月14日(木)「聞香とは」:終了
⑥11月11日(木)「芸能と香」:終了
※講座「聞香とは」では、実践を行います。
掌の聞香炉に心を傾け、一片の香木のかすかな香りを鑑賞する。
この繊細な所作を「聞香」=香を聞く、という美しい言葉で表現します。
初めての方でも気軽にお楽しみ頂けます。
場所は柿傳9階茶席、時間は(A)午後1時半~3時と、
(B)午後3時半~5時の
2組に分かれます。 |
| 場 所 |
柿傅7階安与ホール |
| 会 費 |
1万8千円(全6回分) |
| 申 込 |
受付終了 |
|
| |
畑正高氏 略歴
昭和29年、京都生まれ。同志社大学商学部卒業後、渡英。翌年、香老舗 松栄堂に入社。平成10年、代表取締役社長に就任。香文化普及発展のため国内外での講演・文化活動にも意欲的に取り組む。平成16年ボストン日本協会よりセーヤー賞を受賞。環境省かおり環境部会委員、同志社女子大学非常勤講師などの公職も務める。著書に「香三才」(東京書籍)、「香清話」(淡交社)、関連書籍に「香千載」(光村推古書院)他。 |
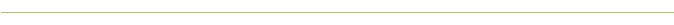
|
田野倉徹也先生企画 第40回【茶室見学会】
向夏の7月、「岡田茂吉ゆかりの茶室めぐり」をテーマに、箱根・熱海にて茶室見学会を行います。
前半生を実業家として、後
半生は宗教家として、明治・大正・昭和期の日本に足跡を遺した岡田茂吉(一八八二〜一九五五)は、第二次大戦末期の昭和十九年から「神仙郷」の造営に着手し、その中に美術館を計画しました。昭和二十七年、箱根美術館を開館。令和三年には、箱根美術館が建つ「神仙郷」が、国の名勝の指定を受けました。今回は
「神仙郷」内に建つ通常非公開の国登録有形文化財「神山荘(旧藤山雷太別荘)」、茶室「山月庵」などを見学します。
昼食は、明治二十八年、皇室の宮ノ下御用邸として造営された富士屋ホテル旧御用邸菊華荘にて頂きます。
午後は昭和五十七年に箱根美術館の姉妹館として開館されたMOA美術館へ。光琳屋敷」や「樵亭」など、茶室や数寄屋にテーマを絞り、岡田茂吉の建築・芸術思想や世界観に触れます。呈茶もございます。ぜひ、ご参加下さい。 田野倉徹也
|
| |
| 講 師 |
田野倉徹也氏(数寄屋建築家) |
| 日 程 |
令和6年7月16日(火)
8時15分:小田原駅周辺に集合
(時間厳守)
16時30分頃:熱海駅周辺にて解散予定
見学
①箱根美術館
茶室「山月庵」(通常非公開)、
国登録有形文化財「神山荘」(通常非公開)など
②MOA美術館
「光琳屋敷」、「樵亭」など
|
| 会 費 |
2万8千円 昼食代、呈茶代、バス代込み(昼食は「富士屋ホテル 旧御用邸 菊華荘」にて税込5,500円の献上御膳。MOA美術館にて呈茶あり)
※小田原駅周辺集合・熱海駅周辺解散
小田原駅→①→②→熱海駅の間は全て小型バスで移動します(正座席のみ使用/補助席なし)。
※道が狭い場所など、安全を確保するために、バスを降りて目的地まで少し歩く場合があります。
複数組にわけて交代で茶室に入るため、お待ち頂く時間がある事を、ご了承頂ければ幸いです。
|
| 定 員 |
22名 |
| 申 込 |
申込受付:葉書またはメールにてキャンセル待ち受付中
【葉書の場合】
〒160-0022 新宿区新宿3-37-11-8階
茶の湯同好会 第40回茶室見学会係宛
【メールの場合】chaji@kakiden.com
(会員番号、氏名、住所、電話番号を明記してお申込下さい)
|
|
| |
田野倉徹也氏 略歴
1978年生。東京大学・同大学院修了。鹿島建設株式会社を退社後、田野倉建築事務所を設立。近代数寄者の茶室や能舞台の木割研究を下地に、伝統的な数寄屋や社寺の実作を手掛ける。にっぽん文楽組立舞台を設計するなど、伝統芸能に関する造詣も深い。 |
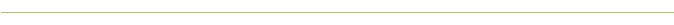
|
第52回【茶道夏期大学】 申込受付開始しました
|
| |
| 講座内容 |
7/28(日)
|
岩井素心氏(立花師)
対談:熊倉功夫氏(MIHO MUSEUM 館長)
手嶋龍一氏(ジャーナリスト・作家) |
7/29(月)
|
永樂善五郎氏(千家十職 土風炉・焼物師 永樂家十八代)
川合正朝氏(美術史学者) |
7/30(火)
|
渡辺 潤氏(家元教授 表千家同門会 理事)
猶有斎 千 宗左氏(表千家当代家元)
而妙斎 千 宗旦氏(表千家十四代家元)
|
|
| 講 師 |
(講演日順)岩井素心氏、熊倉功夫氏、手嶋龍一氏、永樂善五郎氏、川合正朝氏、渡辺潤氏、
猶有斎 千宗左氏、而妙斎 千宗旦氏 |
| 日 時 |
令和6年7月28日(日)29日(月)30日(火)
午後1時~4時15分 |
| 会 費 |
2万円(資料代含む、懇親会費1万1千円別途) |
| 定 員 |
茶道夏期大学:150名(机有り)
7月30日懇親会:80名(夏期大学参加者のうち希望者のみ)
定員となり次第締切とさせていただきます
|
| 申込方法 |
申込受付:キャンセル待ち受付中
葉書に会員番号・氏名・住所・電話番号を明記の上、下記宛にお申込下さい
〒160-0022 新宿区新宿3-37-11-8階
茶の湯同好会 茶道夏期大学係
※受付済の方には案内状をご送付致します。 |
|
| |
●懇親会 7月30日は懇親会を午後4時45分頃より柿傳6階古今サロンにて開催致します。
(希望者のみ 会費11,000円・定員80名) |
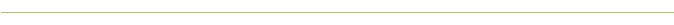
|
|
【表千家茶事教室】
この度、貴重なご縁を頂戴し、長澤保人様(表千家教授)のご指導により茶事教室を再開する運びとなりました。表千家流の方に限らず、他流の方、また初心者の方にも、分かりやすくご指導させて頂きます。
|
| |
| 講 師 |
長澤保人氏(表千家教授) |
| 日 程 |
第1回 令和6年3月15日(金):終了
第2回 令和6年5月17日(金):終了
第3回 令和6年9月27日(金)
第4回 令和6年11月29日(金)
|
| 場 所 |
柿傳9階茶席 |
| 席 入 |
午前11時 |
| 受 付 |
席入30分前に6階にて |
| 定 員 |
30名(茶の湯同好会会員) |
| 会 費 |
2万円(水屋料含) |
| 申 込 |
※第3回以降は、改めて申込期間等を告知致します。
|
|
| |
長澤保人氏 略歴
昭和25年、東京都青梅市曹洞宗高徳寺で生まれ、駒澤大学仏教学部卒業後、青梅市常秀院、高徳寺、埼玉県飯能市心應寺の住職を歴任し、檀徒教化と各寺院の伽藍整備に尽力、令和元年に退董。
昭和45年より表千家茶道を学び、心應寺内に茶道教室を開き現在に至る。
|
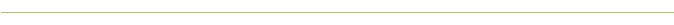 |
【名物籠に学び、籠を編む3】 池田瓢阿先生 令和6年9月からの新講座です
不昧公ゆかりの隅田川菓子器(花入)を編みます
ある時、不昧公が江戸での茶事に、白魚を籠の八寸にのせて客に出した。その八寸は隅田川の白魚漁の網を模した青竹の籠で、客の本屋了雲がもらい受け、色抜きをしてお見せたところ、不昧公は「隅田川」と箱に書付け、了雲は喜んで持ち帰ったという。そんな謂れを持つ菓子器を作ります。八寸にも、筒を入れれば花入にも使えます。 池田瓢阿 |
| |
| 講 師 |
池田瓢阿氏(竹工芸師) |
| 日時・内容 |
令和6年9月~12月分 毎月第1木曜日(10月は第5木曜日)
①②(講座)午後1時半~3時
③④(実習)午後1時半~3時半
令和6年
① 9月 5日(木):籠の基本(講座1)
②10月31日(木):名品解説(講座2)
③11月 7日(木):隅田川菓子器を編む(実習1)
④12月 5日(木):隅田川菓子器を編む(実習2) |
| 開 講 |
令和6年9月5日(木) |
| 場 所 |
安与ホール(安与ビル7階) |
| 定 員 |
20名(茶の湯同好会会員) |
| 会 費 |
2万(全4回分、材料費別途)
材料費:1万円6千円(隅田川菓子器/白竹/筒代込み)
※少人数による実習を伴う為、誠に恐縮ですが、通常の会費よりも
値上げさせて頂いております。何卒ご理解頂ければ幸いです。 |
| 申 込 |
TEL.03-3352-5120 |
|
| |
池田瓢阿氏 略歴
1951年、東京生まれ。1993年、三代目瓢阿を襲名。古典の基本を押さえつつ、竹芸の新しい可能性を探って精力的に活動。また、竹に関する茶道具や民俗などの研究に力を注いでいる。日本橋三越本店や柿傳ギャラリー等において定期的に個展を開催。「近代の茶杓」「籠と竹のよもやまばなし」(淡交社)など著書多数。 |
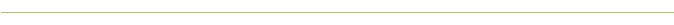 |
【 茶陶が語る茶の湯の歴史3 】 赤沼多佳先生
今日まで伝わる茶道具は、各時代の茶風を具体的に教えてくれます。なかでも茶陶は種類が多く、それぞれが誕生した時代の様相を窺うことができます。今回は花入、水指、茶碗、香合など、器種別に紹介しながら茶の湯の歴史を顧みたいと思います。(映像を使用) 赤沼多佳 |
| |
| 講 師 |
赤沼多佳氏 |
| 日 時 |
[前期]
①令和7年6月20日(木):終了、②7月18日(木)、③9月19日(木)、
④10月17日(木)、⑤11月21日(木)、
[後期]
⑥12月19日(木)、⑦令和7年2月20日(木)、⑧3月13日(木)、
⑨4月17日(木)⑩5月15日(木)
毎月第3木曜日(3月は第2木曜日)
午前10時半~12時 |
| 開 講 |
令和7年6月20日(木) |
| 場 所 |
安与ホール(安与ビル7階) |
| 会 費 |
3万円(全10回)、前期・後期(各5回分)分納可 |
| 申 込 |
TEL.03-3352-5120 |
|
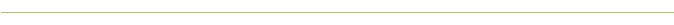 |
一般公開 特別講座
【数寄者の実践 - 歴史を踏まえた茶室づくり】 田野倉徹也先生 終了しました
「一生涯に自分の住宅を五回だけ新築して見たい」と近代数寄者・高橋箒庵は遺しています。今日、マイホームは一生の買い物。家の中につくるたったひとつのお茶室が、歴史とこれからの茶の湯を繋いでいくために、文献と実践から数寄屋普請を学びます。今回は、「つくる」視点から茶室についてお話しします。 田野倉徹也 |
| |
| 講座内容 |
⑥令和元年11月14日(木) 現代茶室論議 - 数寄者の今と昔 |
| 講 師 |
田野倉徹也氏(数寄屋建築家) |
| 日 時 |
平成30年12月~令和元年11月
隔月第2木曜日
午前10時半~12時 |
| 場 所 |
安与ホール(安与ビル7階) |
| 会 費 |
会員:1万8千円 一般:2万1千円 (全6回) |
| 申 込 |
受付終了 |
|
| |
田野倉徹也氏 略歴
1978年生。東京大学・同大学院修了。鹿島建設株式会社を退社後、田野倉建築事務所を設立。近代数寄者の茶室や能舞台の木割研究を下地に、伝統的な数寄屋や社寺を実作を手掛ける。山下和美氏の漫画『数寄です!』には蔵田徹也として登場し、数寄屋を解説する役割を担っている。にっぽん文楽組立舞台を設計するなど、伝統芸能に関する造詣も深い。
|
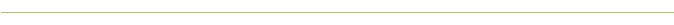
|
【禅の風 - 『無門関』】 泉田玉堂先生
茶の湯をこころざす人にとって有用であり、茶席にも掛けられる言葉に出会う禅語録『無門関』一巻を拝読します。
四十八則の話から成り立っていますが、いずれも「自己とは何か」すなわち「個」の問題と、「他者へのいたわり」すなわち、自ずからなる「共同体」(一座建立)への指向の問題が、はらまれています。
茶の湯にたずさわる人には、点前作法のみにとどまることなく、奥深い精神である「和敬静寂」を求めるための指針となるでしょう。 泉田玉堂
|
| |
| 講 師 |
泉田玉堂氏(大徳寺第五三0世住持) |
| 日 時 |
①令和6年5月8日(水):終了
②7月3日(水)
③10月2日(水)
④12月4日(水)
⑤令和7年3月5日(水)
隔月第1水曜日(5月は第2水曜日)
午後1時半~3時 |
| 場 所 |
安与ホール(安与ビル7階) |
| 会 費 |
1万5千円(全5回) |
| 申 込 |
TEL.03-3352-5120 |
|
| |
泉田玉堂氏 略歴
1942年新潟生まれ。早稲田大学卒業後、立花大亀老師につき出家。次いで瑞泉僧堂の松田正道老師に参じて印可証明を受ける。1993年より奈良大宇陀の大徳寺派松源院に住す。 |
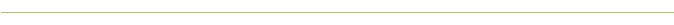
|
【新年茶会】 終了しました
日頃、お世話になっている茶の湯同好会会員の皆様とご一緒に、新しい年を寿ぎたく、吉例の新年茶会を催します。
今年も、柿傳の安田眞一と、柿傳ギャラリーの安田尚史の我々兄弟で釜をかけさせていただきます。
お陰様でご好評を頂いているすっぽん出汁の雑煮椀や柿なますなどの祝膳をお召し上がり頂き、空くじなしの福引もございます。
未熟な我々ですが、精一杯、務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 安田眞一 安田尚史 |
| |
| 日 時 |
令和6年1月25日(木)
席入 ①午前10時 ②午前11時半 ③午後1時半 ④午後3時
一席30名様
|
| 茶 席 |
柿傳9階残月亭(安与ビル9階) |
| 祝 膳 席 |
古今サロン(同ビル6階) |
| 会 費 |
1万9千円(祝膳含) |
| 申 込 |
受付終了
|
|
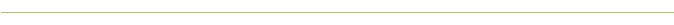
|
令和六年 第20回【茶の湯同好会茶会】
茶の湯同好会茶会を開催させて頂きます。席主は、お忙しい中、今回も潮田洋一郎様にお引き受け頂きました。誠にありがとうございます。
※第二十一回以降については未定です。改めて告知致します。
|
| |
| 日 時 |
第20回10月18日(金)
席主:潮田洋一郎氏
※詳細は、改めて告知致します
|
| 茶 席 |
柿傳9階残月亭(安与ビル9階) |
| 酒 飯 席 |
古今サロン(同ビル6階) |
| 会 費 |
※詳細は、改めて告知致します |
| 申 込 |
※詳細は、改めて告知致します |
|
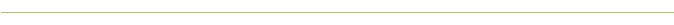
|
【三千家歴代2】 熊倉功夫先生 現在、申込を受け付けております
十八世紀中期ごろから表千家では如心斎、裏千家では一燈宗室、官休庵では直斎が活躍して、いわゆる七事式が誕生しました。ここから茶の湯は大きく変わりました。やがて幕末から明治維新、文明開化期には、三千家は困難な時代を迎えますが、裏千家の玄々斎は立礼を発明し、新しい茶の湯が始まります。現代の茶までその歴史をたどってみることにしましょう。 熊倉功夫
|
| |
| 講 師 |
熊倉功夫氏(日本文化史、茶道史研究家) |
| 日 時 |
①3月29日(金):終了、②4月12日(金):終了、③5月10日(金):終了、
④6月14日(金):終了、⑤7月12日、⑥9月13日(金)
*毎月第2金曜日(3月は第5金曜日)
*午後1時半~3時
|
| 場 所 |
7階安与ホール |
会 費
|
1万8千円(全6回
) |
| 講師略歴 |
日本文化史専攻。茶道史、寛永文化、日本の料理文化史、民藝運動などを研究。
現在、MIHO MUSEUM館長、国立民俗学博物館名誉教授。 |
| 申 込 |
申込受付中
申込多数の為、3人掛けとなる席がございます。
TEL.03-3352-5120 |
|
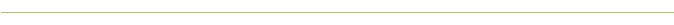
|
【裂の魅力、仕覆の仕立て方】 終了しました
土田家は千家十職として、茶入の仕覆を中心に、裂や組紐を用いた茶の湯の道具を手掛けています。この講座では、袋師として仕事や茶道で使う裂の種類、他の道具との関係などの講義に加えて、毎回、実作の制作工程を見ていただきながら、皆様との対話を楽しみたいと思っています。 土田半四郎 |
| |
| 講 師 |
土田半四郎氏(千家十職 袋師) |
| 日 時 |
平成29年10月17日(火)、12月5日(火)、平成30年3月20日(火) 、5月22日(火) 、
7月25日(水)終了、10月23日(火)
*午後1時半~3時 |
| 場 所 |
7階安与ホール |
会 費
|
1万8千円(全6回
) |
| 講師略歴 |
2014年、十三代土田半四郎を襲名。土田家は、千家十職の一つである袋師。
裂地を用いた仕覆や袱紗のほか、糸や織物を用いた道具を手掛ける。
|
| 申 込 |
TEL.03-3352-5120 |
|
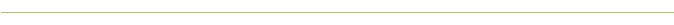
|
【『山上宗二記』を精読する】 竹内順一先生 令和6年7月からの新講座です
千利休に二十年余間学んだ山上宗二は、四十五歳の天正一六年(一五八八)から唐物名物の所在リストを執筆する。茶の湯の点前を約三〇〇日費やして学んだ弟子に、印可状として伝授するためである。伝授者は、計十三名。世にいう『山上宗二記』である。本講座では、茶の湯発展史を概観し、茶壺から書き出す詳細版を読む。 竹内順一 |
| |
| 講 師 |
竹内順一氏(東京藝術大学名誉教授)
|
| 日 時 |
[前期]
①令和6年7月26日(金) 茶の湯の歴史 その1
②9月20日(金) 茶の湯の歴史 その2
③10月25日(金)
④11月22日(金)
⑤12月20日(金)
[後期]
⑥令和7年2月28日(金)
⑦3月28日(金)
⑧4月25日(金)
⑨5月23日(金)
⑩6月日20日(金)
毎月第4金曜日(9月、12月、6月は第3金曜日)
午後1時半~3時 |
| 開 講 |
令和6年7月26日(金) |
| 場 所 |
柿傅7階安与ホール |
| 会 費 |
3万円(今期10回)、前期・後期(各5回分)分納可
全20回のうち10回を今回募集致します。 |
| 申 込 |
TEL.03-3352-5120 |
|
| |
竹内順一氏 略歴
1941年生。東京芸術大学美術学部芸術学科(工芸史専攻)卒業。五島美術館学芸員、学芸部長、東京芸術大学美術館教授・同館長、東京芸術大学教授を経て、現職。 |
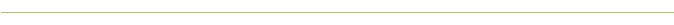
|
一般公開 第43回定期講演会
【都機工房の営み-母・志村ふくみとともに】 志村洋子先生 終了しました
都機工房の名前の由来。工房がある京都嵯峨は月の名所でもあります。随分昔になりますが、嵯峨の工房に新しく名前を付けようと思い立ち、道元の『正法眼蔵』第23「都機」より都機工房と命名しました。都機は万葉がなで月の意味です。
工房での仕事は多様な染織に加えて、藍を建て染めて織ります。藍は月の運行のリズムにそって育てています。藍の神秘的な色彩を中心にお話いたします。 志村洋子
|
| |
| 講 師 |
志村洋子氏(染織家、随筆家) |
| コーディネーター |
竹内順一氏(東京藝術大学名誉教授)
※誠に恐れ入りますが、都合により変更となりました。 |
| 日 程 |
令和4年6月11日(土) |
| 時 間 |
午後2時~3時半 |
| 場 所 |
安与ホール(安与ビル7階) |
| 会 費 |
会員:1千8百円 一般:2千円 |
| 申 込 |
終了しました |
|
| |
志村洋子氏 略歴
「藍建て」に強く心を引かれ、30代から母・志村ふくみと同じ染織の世界に入る。
平成元年に、宗教、芸術、教育など文化の全体像を織物を通して総合的に学ぶ場として「都機工房(つきこうぼう)」を創設。
著書に『色という奇跡』、ふくみ、息子・昌司との共著『夢もまた青し 志村の色と言葉』。作品集に『しむらのいろ』『オペラ』がある。
平成25年に芸術学校アルスシムラをふくみ、息子・昌司とともに開校。
|
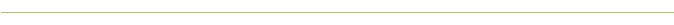 |
| Copy right (c) 茶の湯同好会 無断転載・複写を禁じます。 |